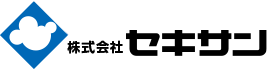地震に強い日本の伝統建築
紀元前5世紀のギリシャ文明を象徴するパルテノンの列柱構造が耐震建築の模範と考えられるのは、縦線(柱)と横線(梁(はり))で空間を区切る主要素(架構(かこう))となっている点である。手加工で切りそろえた巨石を木製のダボ(接合材)でつなぎ、積み重ねた柱は、柱上の梁と屋根の荷重を柱頭のキャピタルで受けて礎石、基壇(きだん)から地盤へ伝達するとともに地震動による水平方向への力に対しても安定して架構を保持する機能を持つ。
日本建築の基本構造はパルテノンから1000年以上遅れ、仏教とともに朝鮮半島の百済からもたらされた。飛鳥寺の建造(6世紀末)から奈良、平安時代にかけ日本全国に広まった架構は驚くほどにパルテノンの列柱に似ている。当時はまだ巨木があったのか、太い柱は直径が高さの10分の1以上もあった。柱頂部は頭貫(かしらぬき)で柱どうしをつなぎ、柱下端は平らに加工された礎石が基壇上に据えられる。重い屋根を受け持つ桁材は斗栱(ときょう)(組物(くみもの))を介して柱へ荷重を伝達する。この斗栱は深い軒を支える役割を持ち仏教寺院建築を印象づける。
地震で柱が傾いたときに斗(ます)と肘木(ひじき)がそれぞれ逆方向に傾斜し、上部の桁(けた)と屋根を水平に保つ働きは、実大架構の振動実験で確認されている。柱脚部の足固めや頭貫の下段に内法貫(うちのりぬき)を入れた事例(国分寺金堂)もあり、柱どうしをつなぎ耐震性を高める工夫と考えられる。